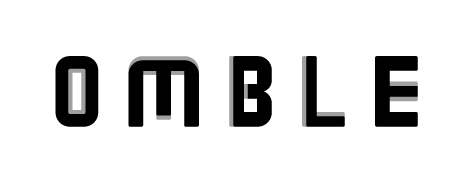2023/03/28 16:44
陶芸との出会いを教えて下さい
数年前まで陶芸とは全く無縁でした。美大で空間デザインを学び、空間設計事務所に就職しました。
デザイナーとして勤務していた27歳の時、インテリアデザインを手掛けていました。空間や大きな店舗など、大規模なデザインに携わっていましたがなかなか一人では細部までこだわれず、少しもどかしさを感じ始めていました。いずれ独立したいと思いながら働いていた時に、デザイナーとして幅を広げたく、素材を知るために陶芸教室に通い始めた事が陶芸との出会いですね。
初めて触った土。土をこねたの感触に感激しました。今までの仕事のようにデザインで終わるのではなく、成形まで全部自分で完結できる陶芸にすぐ魅了されましたね。すぐに学べるところを探して、一番近かった笠間陶芸大学校を受験。合格して一期生として入学し2年間、陶芸漬けの生活でした。
国が関わっているだけあって非常に施設の設備、ロケーションが良く、非常に満足の行く2年間でした。一学年10人ほどしか入学できず、一人一台ろくろがあり、粘土も使い放題、焼き放題、学費は年10万円ほどでした。陶芸家を目指している方は是非一度調べてみて下さいね。
卒業後、杉並区の実家の一部屋に小さい電気窯を置いてゴブレットやペットボトルの一輪挿しを作り始めました。友人と一緒に一軒家を借りたり転々として、現在は池袋で作陶しています。作陶歴は5年ほど経つでしょうか。陶芸家として初の個展は、目白のギャラリーさんでした。キューピーやクマ、カエルなどのオブジェを作ったんですが、その際に知人に電気窯を安く譲って頂きました。植木鉢を作り始めたのは2年ほど前からですね。

作陶の手順を教えて下さい
使用している土は作品によって変えますが、殆どの場合は、ざらざらして軽いロットという白土を使い、電動ろくろで成形しています。
成形した器体を乾かし、削ります。削った後に、石などで軽く叩いたり押したりしてちょっとした凹凸を表面につけ、乾かします。乾燥後、化粧土を塗って素焼きをします。
素焼きが終わると施釉ですね。作品によりますが、6~7種類くらいの釉薬を、筆だったりスポンジだったりで丁寧に塗り重ねていきます。釉薬を複数重ね塗ったり、逆に重ねなかったり、複雑且つ自然に表情を出すよう計算しながら施釉しています。
この工程で、下に塗っている釉薬と上に塗っている釉薬の質の差で釉が剥がれ、凹凸やヒビ、ライン、クレーターが出るのを作風として取り入れています。是非手にとって見て頂きたい箇所です。剥がれ方が複雑になったり、箇所によっては剥がれないようコントロールしています。
釉薬は、織部、クロム、コバルト、銅など、緑になるようなものは殆ど使っていると思います。作品によっては、金彩も施します。
施釉後は本焼きに移ります。電気窯を使用していて、温度は1250℃まで上げ、最低二回焼くので、素焼きと合わせて最低三回は焼いていることになりますね。
二度本焼きをした後、金を入れてもう一度焼く事もありますし、上絵の具を塗ってもう一度焼く事もあります。二度本焼きをした後、何も施釉を加えず渋みを出すためだけにもう一度焼く事もあります。
窯から出すときが一番好きですね。
自分の作品がどうなっているのか分からずに、新しく出会うのが毎回楽しみです。

作品について
人生で唯一行った海外がカンボジアのアンコールワット、近くのタ・プローム遺跡(アンジェリーナ・ジョリー主演のトゥームレイダーのロケ地)などに行くほど廃墟が大好きです。
また、神社仏閣、石像についている苔、金属についている錆とか、青銅についている緑青などが、昔からそこに存在するような、歴史的・経年的な要素に浪漫を感じるのでしょう。自然と人工物が混じったような雰囲気に太古のロマンを感じます。金属などでは枯せた表情というのはなかなか作れなく、陶芸でないと表現できないところが私にガッチリ噛み合いました。
ほぼ永遠に、形が変わらないであろう陶器。
そんな陶器に、経年変化を表現した作品を作る事が好きです。
このように時間の流れを考えながら作品に取り入れていますが、今後はより多角的に陸だけではなく海のものも取り入れたら幅が広がるかと思い、取り入れはじめています。

OMBLE:最後までお読み頂きまして有難う御座いました。
波部さん、お忙しいところ、理解出来るまで何度も説明頂きまして有難うございました。
波部さんの世界観が溢れんばかりの作品、私も利用させて頂いております。
新しくチャンレンジしている作品も楽しみにしております!