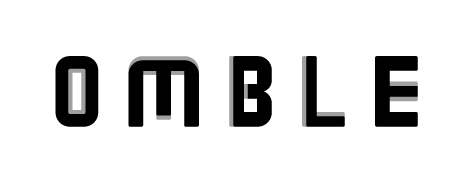2023/01/19 09:06
「工芸とプロダクトの境」をテーマに岐阜県多治見で作陶されている、北川和喜さんのアトリエを訪ねました。OMBLEが取扱う陶芸作家で唯一、鋳込みで作陶しており、手作りの唯一性の良さと、均一且つ統一性のもつ美しさを併せ持った作品が魅力です。

陶芸との出会い
出身は京都です。大学まで京都に住んでデザイン学科を卒業後、多治見にある陶磁器意匠研究所を卒業した縁で現在も多治見市で作陶活動をしています。
意匠研究所を卒業後、多治見で陶器の商社に4年勤め知識を深めました。退職して陶芸一本で独立した直後にコロナ禍に入り陶器市やイベントが激減してしまい、間借りしているメーカーさんの仕事をもらいながらコツコツと作陶していました。お陰様で現在はお取引しているところも増え、陶芸一本で生活出来ています。
どのようにして作陶されているのでしょうか?
石膏型を使って同じ形状・サイズの作品を繰り返し作る「鋳込み」という技法で作陶しています。
まず、必要なのは「泥漿(でいしょう)」です。鋳込み用泥漿は、粘土・水・珪酸ソーダをミキサーでよく混ぜた液状の粘土で、轆轤を使って作陶する方法とは全く異なり、粘土に空気が入って…などの心配がそもそもありません。
土は、白磁のケーキを500キロ単位で大量に購入しています。結構、格安で卸してもらっています。この辺が多治見の良いところですね。この土をちぎって水に一日ほど浸します。珪酸ソーダを少量混ぜることで流動し、鋳込み易くなります。これに顔料を入れることで、色々な色が入ります。現在使っている色は15色程度でしょうか、顔料同士を調合して色を出しているものもあります。ひしゃくで泥漿をすくってみて、糸をひくように流れ落ちる程度に調整します。置いておくと乾燥したり蒸発したりするので、その度に水などを少量入れて調整する必要があります。これが「泥漿」です。顔料を複数混ぜる事で、「Marble」などの泥漿を作ることができます。

磁器と陶器の違いについて
磁器と陶器は成分が異なり、磁器は、長石30%、珪石40%、粘土30%。陶器は、長石10%、珪石40%、粘土50%の比率です。つまり、長石を多くすると、良く熔けて磁器になり、少なくすると陶器になります。
長石と珪石はガラスになる成分で、磁器は、陶器よりガラス質を多く含む事によって、陶器は吸水率を持ちますが、磁器は持ちません。
陶器は気泡がありガラス量が少ないので光を通さず、磁器は、半分以上がガラス質になっているので光を通します。ガラスと陶器の間が磁器と言えると思います。磁器はガラスに近いですが、陶器の良さも持っていると感じますね。
磁器を焼成する温度は、焼き物の中で最も高温の1200~1400℃で焼成します。陶器は800~1250℃です。
一般的に、鋳込みでは磁器が扱いやすいと言われています。

鋳込みについて
泥漿が漏れないように固定した石膏型をロクロに置いて芯を取ります。簡単に言うと、植木鉢の形をした石膏型に泥漿を流して乾燥すると植木鉢が成形される、という事です。
顔料を複数使用した作品「Marble」を作る前提で話すと、まず複数の顔料(白・青・水色など)を混ぜながら作った泥漿を準備します。
泥漿を容器を叩いて泥漿内の気泡を抜き、鋳込み型に注いでいきます。このMarbleが型についた瞬間だけ色が定着します。あとは馴染んで内側はほとんど色付きません。鋳込み口のぎりぎりまでゆっくりと注ぎ、10分程度様子を見ます。この作業がロクロで言う成形で、植木鉢の形を作っています。
様子見をしている間に、どんどん泥漿の水分が石膏に吸収されて10分後には5~8ミリ程度の厚さに着肉し、型を逆さにして要らない泥漿を全て容器にガバっと排泥します。ガバ鋳込みと呼ばれる所以です。
鋳込んでから30分程度置いたら、手でトントン優しく叩いたり振動を加えながら石膏型を外します。型から外して、余分な鋳込み口を切り落として、断面をスポンジなどで加工します。切りっぱなしだと乾燥時に裂けてしまうことがあり注意すべきポイントです。外側の形状だけ型通りになり内側は少し丸みを持たせています。
これで、成形は完成です。
ほとんどのデザインは、高台も型そのままの形で取ることができ、作品によっては削りの作業が無く、口元を仕上げて成形が完成し、そのまま焼成すします。すでに顔料で色がついているので、素焼きをした後に釉薬をつける作業も必要ではありません。一発本焼きで焼成しています。(ただ、器と花器だけは釉薬を掛けている作品が多いので、その場合は素焼きをした後に釉薬を掛けて本焼きとなります)
色味は調整できますが、模様の完全な再現はできませんので、一点物だと思いながら作陶しています。
Marble以外にも、例えばチューブで型に顔料を予め少し流してから泥漿を流すことで、雨模様のような模様をつけることができ、作品化しています
重色目について
上記の鋳込み工程を単色で3~4回繰り返すことで、3色~4色の層になって成形されます。一成形後取り出し、生乾きの段階で鉋を使って刳り貫きます。どの層まで刳り貫くか、その深さによって浮き出る色が異なる、という訳です。つまり、一番外側に持ってきたい色を最初に流し、乾燥したら二番目の色を、という順序になり最後に流す色が内側の色になります。非常にシンプルに説明しましたが、工程数が段違いになります。

型について
私の場合ですが、型の原型を石膏から作っています。
粉末の石膏を用意して、水と混ぜて化学反応させて、石膏が固まり始めます。固まって乾燥する直前に、おおよその感覚で急いで鉋で削っていきます。刳り貫く作業に近いです。高台の形状もこの時に削っていきます。
回転体だとロクロで石膏を鉋で削りますが、植木鉢の場合は外面のみ作ると良いので、石膏の内側をしっかりと削っていきます。
この原型、型作りが全行程で最も大変で労力が必要な作業で、現在は形状で50個以上、全部で100~150型はあると思いますが、数えたことは有りません。

多治見の四季を教えて下さい
多治見は盆地で、天気予報で報道されることも多々ありますが、夏は暑く、冬は寒いです。気温だけで見ると相当ハードだと思います。
夏の暑さは尋常ではなく、40℃に迫る事も多々あり、出身の京都も暑いですが、ここはレベルが違いますね。
ただ陶芸していると夏の暑さは暑いだけでそこまで問題ではないのですが、雪こそあまり降らない冬、気温が氷点下を下回る日があり、粘土が凍ったりする心配がついて回るので仕事に影響が出ます。冬はアトリエ全体にビニールハウスのように防寒用にビニールで覆い仕事をします。
やはり仕事しやすいのは晩夏から秋と、春にかけてでしょうか。
多治見はレンタルで窯を借りれたり、選べたり、陶芸スペースがあったり、作家にも優しい土地であることから、陶芸家を目指すにはかなり始めやすいと思いますよ。

OMBLE:
最後までお読み頂きまして有難う御座いました。
一つ一つ顔料を混ぜながら作陶する手作りの唯一性が際立つ「Marble」と、派手な色を重ね削ることで落ち着きを持った重色目はプライベートでも使用しています。かなり使い易いですし、映えます。鋳込みならではのガラスのような磁器感がお洒落です。是非一点、手にとってコレクションに加えてください。