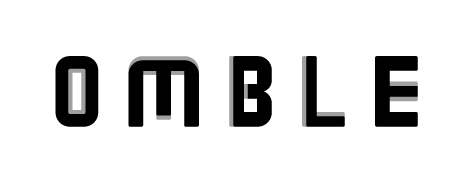2022/12/21 16:02
初雪が降る直前、陶芸家・佐藤恵一氏に会いに金沢のアトリエを訪ねました。

陶芸家への道のり
石川県生まれです。
幼い頃から手先が器用で、他人の作業などをすぐに真似る事が出来たんです。
金沢の高校卒業直前、授業が終わる一週間くらいに、些細な事で教師と揉めた事がきっかけで坊主にして上京しました(笑)一回も東京も行ったことが無かったのですが、先輩宅に居候させてもらいました。野宿もしましたね(笑)引きこもりの逆ですね。親不孝でしたね…
東京から石川に電話するのも、当時は500円のテレカで1分持つか持たないか、でしたね。
そこから主に、高円寺に住まいを構え、六本木、中野、渋谷、原宿などで古着販売やTシャツのデザインなどの仕事を経験しました。同時に音楽活動にも精を出し、下北沢や高円寺で活動していました。
33歳を迎えた頃にはバンド活動もおざなりになり始めて、将来を考えて金沢に戻って陶芸に出会い、働きながら陶芸教室に通い作陶する日々が続きました。今思えば、笠間とか益子とか近いところもあったな…と思ったりしています。
ちなみにバンドのジャンルはハードコア、グランジで、ボーカルを担当していました。シャウトしていました(笑)
2009年前後に現在のアトリエを構え、2016年からインスタグラムのDMを通じて、植木鉢の制作をオーダーされ始めた事をきっかけに、植木鉢の制作に取り組み始めました。ちょうどインビジブルインクがネットで買えなくなったあたりですね。結果的に、自分がやりたいことが器では表現できず、植木鉢で上手くいったと思います。2018年から自身の植木鉢が台湾、香港を中心に売れ始め、有り難いことに次第に中国やシンガポールからもオーダーが入り始めて、勿論日本からも頂き、現在は植木鉢を中心に作陶しているという感じですね。またBaseで販売しようかなぁとも思っています。

金沢・山手の四季を教えて下さい
やはり、金沢は冬の雪ですね!凄いですよ。冬は雪しかないですよ。
雪がもの凄く積もる、豪雪地帯です。1m~2m、平気で積もります。金沢市街と、この山間にあるアトリエでは3倍くらい降雪量が違いますね。
県道や国道は毎日除雪車が作業してくれますのでそこまで問題ありませんが、自宅周辺は自分の除雪機で除雪作業をします。はい、自分の除雪機を持っています(笑)ガソリンを入れて、除雪しています。
石川は年間を通じて「晴れの日は2日に1日」と言われるほど曇っていたり雨や雪が多い土地なんです。一週間晴れない日々もしばしば。このアトリエもほぼ常にジメっています。ですので、一番好きな季節は、乾燥気味の秋や夏でしょうか。土が早く乾く…、仕事が捗るという点ですけども。
春は遅く5月頃に訪れます。夏は暑くエアコンをかけるほどです。秋はクマが出ることも…
クマが住んでいる周辺に人間が住んでいる、という感覚でしょうか。クマやキツネの他にも大きな鹿、ニホンザルが住んでいます。シカとか本当にでっかいですよ!稀に雪の間からキツネを見ることが出来ます。キツネは美しく、特に尻尾が綺麗です。
この土地で、ほとんど毎日作陶をしています。

作陶の手順を教えて下さい
何種類かシリーズを展開しており、シリーズ毎に手順や技法、技術が異なります。
ほとんど企業秘密ですが、出来る範囲でわかり易くお伝えしますね。今も私しか出来ないような植木鉢を試作しています。

まず、こちらのKIKAZARIシリーズは、土練機にかけた黒土を電動ろくろで成形します。前置きとして、作品ごとによって作陶の手順が異なることはご理解ください。
成形後、乾燥させて丁寧に削ります。素焼きの前にオリジナルの技法で白化粧土を全体に掛けた後、素焼きを7~800℃で行うことで、白化粧土を掛けた箇所にヒビやクラックが入っている状態になり、この部分が私ならではの技法で企業秘密です。その後、内側には独自に調合した釉薬をかけ、外側には顔料を掛けて本焼きを行います。
つまり、電気窯で本焼き後、白化粧土に入ったヒビやクラックが取れないようなオリジナルの施工して再度800℃で焼きます。さらにその後、ヒビやクラック部分に九谷焼の和絵具を使って上絵を施します。ヒビやクラック部分に一つ一つ丁寧に主に筆で書いていきます。その後再度800℃で焼きます。その後、更に九谷焼で使っている和絵具で上絵を施してもう一度焼く場合もありますが、処理して完成となります。最低3回、モノによっては4回以上、焼いている事になります。販売価格は焼く回数や手間暇、使っているモノによって異なってきます。

KIHAKUシリーズも、土練機を掛けた黒土の塊を刳り貫く事で成形をします。
土の塊の状態から初めに外側を部分を丁寧に刳り貫き形を作って、内側部分を刳り貫き続け、乾燥前には完成形になっています。ここからKIKAZARIシリーズと同様、白化粧土を掛けて素焼きを行い、取り出した後は化粧土にヒビが入っている状態になります。その後、独自に調合した釉薬を掛けて本焼き後、白化粧土部分に入ったヒビやクラックが取れないようにオリジナルの施工をして再度800℃で焼いて完成となります。
今後の展望について
自分なりの新しい技術や技法を模索し続けたいです。
現在も新作のサンプルを作っています。常に新しい事を模索し続けないとこの世界で生き残っていけない気がしています。奇抜ながらも需要のあるような植木鉢を提案していきたいと思っています。

OMBLE:
最後までお読み頂きまして有難う御座いました。
何度も焼成を繰り返し、ヒビ部分に一つ一つ上絵を施すなど、細かな作業や手間暇を惜しむことなく作られた作品たち。新しい技術や独自の技法を模索し続けながら作陶し続ける佐藤氏の姿に感銘を受けました。
帰路、小学生が集団下校する姿を何気なく見ていると、何やら鈴の音が鳴っていました。見るとランドセルに鈴を取り付けており、熊よけなのかと思った秋の金沢でした。
帰りに急いで寿司食いねぇを食しました。やはり海の幸は日本海に限りますね。