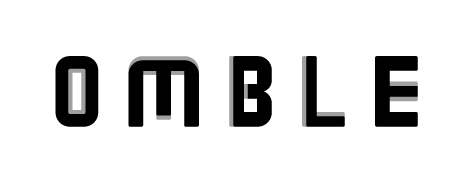2022/11/29 11:09
圧倒的な存在感を放つ「氷裂貫入」を作られている個人作家の栁本美帆さんのアトリエにお邪魔してお話をお聞きしました。
是非最後までお読み頂き、工程を知る事によって更に作品の美しさを感じて頂ければこれ以上に嬉しいことはありません。

陶芸との出会いを教えて下さい
大分県玖珠郡玖珠町で生まれ、愛知県安城市育ちです。18歳の頃まで安城で育ち、名古屋芸術大学美術学部洋画科に入学し油絵を学びました。卒業後2年間働いて貯めたお金で、14歳の時に思い描いた「シャガールのような人生を送りたい」という夢を叶えるため渡仏しました!
ディジョンで1年、パリで1年、合計2年半のフランス生活の中で芸術は身近なものと体感しましたね。ボルドー、ストラスブール、イタリア、ベルギー、ドイツなど、様々な地へ旅もしました。当時は物価が安く、まだEU前、フランス・フランでしたね。パリ滞在中、以前から興味があったガラスか陶芸どちらかをやろう!と決意し帰国。働きながら陶芸教室に通い始めました。営業時間内だったら何時に来ても一日居ても良い、という教室で1年以上通っていました。その後は轆轤を買って自宅で作陶し、陶芸教室の窯で焼いてもらう、といった感じで3年間くらい籍を置いていました。
興味があるとやってみよう!という性格でして、整体師として働いたり、機械設計士にもなりました!2DのCADも、3DのCADも扱えますね(笑)
友人から誘われ初めて展示会をした際、東海テレビから「陶芸作家」として紹介された事をきっかけに本格的に陶芸家を目指すようになりました。働いていましたので、平日は遅くまで残業して、土曜日はリカバリー、日曜日に作陶するというスケジュールでした。
機械設計士として勤めながら年に1回ほど個展を行っていましたが、より高い技術習得のため愛知県窯業技術専門学校で1年間学びました(第一期生はOMBLEでも取り扱っている竹内真吾氏で、同校の非常勤講師の先生でした!)。
翌年、陶芸教室で講師として働きながら瀬戸に工房を構えて本格的に制作を始め、2019年ここ瀬戸赤津に築窯し、現在に至ります。
瀬戸の赤津は山に近く、市街より少し気温が低く、山の天気なので夏でも夜は涼しく、故郷の大分県玖珠のおばあちゃんの家の気候に似ています。冬はもの凄く寒く、更にアトリエや自宅は築100年以上の古民家なのでめちゃくちゃ寒いです!

作陶の手順を教えて下さい
2種類の土を調合して使っています。黒泥に楽白という土を混ぜて使っています。
土練機は持ってないので、全て手作業でコネコネしてから電動ろくろで作陶します。
この時に大きめのコップを作るように成形をします。乾燥させてから、半乾きの時に高台を削って、本体部分を削ってからサインを入れてから素焼きします。
素焼きの温度は900℃と他の作家さんと比べても高い温度で行います(通常は700~800℃)。温度を900℃まで上げる事によって、粘土の中の木節成分が焼ききれるので、作品の特徴である「氷裂貫入」の制作上の問題であるピンホールが出来にくくなるのではないか、という予測です。
いよいよ氷裂貫入ですね。釉薬の工程を教えて下さい
素焼き後、窯の中で表面についた埃を取り除く為に、スポンジを使って丁寧に丸洗いします。食器を洗うようにジャブジャブと洗い流して、1日かけて完全に乾かします。
乾燥後、撥水剤を釉薬が垂れきって欲しい箇所に塗り、始点と終点を決めます。釉薬は長石や石灰石、自然の灰を使い、独自の調合でブレンドしています。
いよいよ釉薬を塗るのですが、釉薬をかけるのでは無く、私の場合は、「釉薬を手で塗り込み」ます。「盛る」イメージです。塗り込んだ釉薬が乾くとまた塗り、それが乾くとまた塗る。これを5層程度にわたって塗り込む事で作品に釉薬のボリュームが生まれます。独自に調合している釉薬が、水分が多い釉薬ではなく、お好み焼きのタネのような釉薬なので塗り重ねる事が出来るんです。時期によりますが、だいたい2日間かけて5層塗り重ねるイメージですね。作品外側の厚みは5層重なっている釉薬、内側は2層程度の釉薬の厚みにより出来たものです。作品下側の灰色部分は焼締めの状態です。

氷裂貫入とは…
「貫入」とは器表面に施している釉薬の表面にあるヒビを指します。「氷裂貫入」との出会いは訓練校で、見た瞬間、恋に落ちたような気持ちになりました。
氷裂貫入は伝統工芸で、ヒビが複数の層にのように重なって入っているもので、亀甲貫入や薔薇貫入との別称もあり、今から800年前に栄えた中国南宋時代に作られた青磁の作品に見受けられました。
貫入も氷裂貫入も生地と釉薬の収縮率の差から生まれるもので、焼成から冷めていく過程の200℃前後から徐々に入ってきます。貫入が入ってくるカリン♪カリン♪という「音色」は神秘的です。
比重が重い釉薬を厚くかけるので、施釉には技術やコツと手間暇が必要になります。その特性により、非常に歩留まりが悪い、稀有な作品で全てが一点物となります。

本焼きについて
分厚い釉薬でサンドイッチしているという事もあり、目に見えない水分を完全に乾かすために100℃で5時間くらい乾燥させてから、肌で水蒸気が出ないかどうか確認して、いよいよ本焼きさせます。
本焼きは、還元も出来る電気窯を使っていて少し低め、1218~20℃くらいまで温度を上げます。氷裂貫入は200℃前後から徐々に入ってくるので、70℃くらいまで冷ましてから徐々に窯を開けていきます。40℃前後まで下がってから取り出して、後処理をしてようやく完成になります。
氷裂貫入の特徴として水に濡れると模様が淡くなり消えたように見えます。
乾く過程で再び貫入が浮き出てくる様は幻想的です。植物を育て水をやり日に当てる中で、その過程も是非楽しんで頂けたらと思います。
より氷裂貫入の美しさが際立つ鉢皿もついていますので、是非一緒に使って頂けたらと思っています。氷裂貫入で平皿を作り始めたのは私だと思っているのですが、より綺麗に見て頂きたいが為にフチを無くしたフラットプレートも作っています!
氷裂貫入の美しさを多くの方に知ってもらいたい。その為には、作り続けるしか無いと思っています。

OMBLE:最後までお読み頂きまして誠に有難う御座いました。
氷裂貫入が出来るまで工程をお知り頂いた上でもう一度作品を見ると、また違った見方が出来ると思います。実際に植物を植えて、水を上げてみて下さい。美しい瞬間に出会える、シアワセな時間になると思います。
栁本さん、昼過ぎからお話して、気づけば暗くなっていました。ご本人のお名前とアトリエの名前通りの素敵な方でした。長時間に渡って丁寧に詳しく楽しくお話して頂いて有難う御座いました。
栁本美帆 https://omble.base.shop/categories/4808702