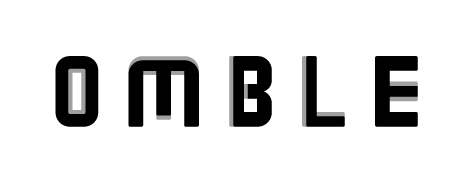2022/11/23 17:29
私の中でも、特に「謎の陶芸作家さん」でした平松龍馬さんを訪ねて千葉の佐原を訪ねました。

佐原はどのような土地ですか
出身は千葉県で、大学卒業後、陶芸を学んだのは益子の窯業支援センターです。益子を出て実家近くで開窯し、2016年に佐原に移ってきました。今後も千葉で作陶するつもりです。
佐原は小江戸と呼ばれいて、利根川水運の中間地点として栄えた町で、昔からの商人の方が作られた江戸情緒が溢れる町並みが残っていて、400年の歴史がある町だそうです。このあたりの土地をもっていたのが伊能家で、最も有名なのは日本国中を測量して実測による日本地図を完成させた伊能忠敬です。アトリエは、この伊能忠敬記念館のすぐそばです。
橋を渡ればすぐ茨城県で、アントラーズで有名なカシマスタジアムは30分くらいで訪れます。友人が見つけてくれたのが今のアトリエで、気候は都会と比べて少し寒い程度で、作陶には全く問題ありません。

作陶の手順を教えて下さい
全て手作業で行います。
まず自分で土を練ることからスタートして、全て「手捻り」で作っています。
ロクロで成形するのと比べて効率が全く違って手間暇がかかります。おそらく伝わらないと思うんですが、ロクロだと自分には少しスピードが早すぎて、瞬間芸みたいに感じて、結局ダメなんですね。ちょっとずつ、ちょっとずつ組み立てるのが自分には向いてるんだなぁと思います。
例えば植木鉢だと、まず高台を作ってから、粘土を手でコネコネして四辺の壁を作って、それを繋いでくっつけていく。簡単に見えますが経験が必要で手間暇がかかります。

シリーズによって入っているヒビや裂け目は、最初の手捻りで成形をする時に粘土の折りたたみ方で意識的にヒビを入れています。粘土と粘土を手作業でくっつけていくと必ず違和感が出てくるので、小さな粘土をコネコネして貼り付け違和感を無くしていく。最初から完成形を意識してヒビやクラックを付けながら歪ませたりしていく。
成形した後、全体をスポンジで少し磨いて、より頑丈にするために泥で内部を丁寧に固めていきます。乾燥前に削りを入れる作業に入ります。削った後、下絵の具を何色か重ねています。例えば、一番下に黒色を塗り、その上から青を塗ったりします。下絵を塗って乾かしてから、素焼きを750~800℃で行います。

素焼き後に、透明釉を塗ってから灯油窯で本焼きを1250~1260℃で行います。灯油窯はマイコンで制御できる電気窯と違って、一時間に一回程度少しずつ空気量や灯油量を上げないといけないんです。更に室内がサウナ状態になります。ただ、酸化と還元の中間がとれる、火が入ることで発色が入る、この微妙な感じが好きで使っています。
本焼き後、上絵を施します。例えば金彩の作品は本焼きに上絵として金を塗った後、800℃近くでもう一度焼き付けてようやく完成します。

作陶の想い
窯の中で自然に歪んだりとか、ヒビが入ったりする作品が元々好きでした。ただ、なかなか狙って出来るものでも無いんです。だったら、最初からヒビをつけちゃえば良いんじゃね?ということで、たどり着いた技法を使って作陶することが多いです。
アンモナイトに代表される化石や金銀などの鉱物、龍や鬼から着想を得て制作しています。はい、よく見るYouTubeのジャンルはオカルト系で、作業しながら良く聞いています。特に心霊スポット凸や廃墟めぐり系の動画が好きです。
突き抜けた作品を作陶したい!という想いがあり、常に進化し続けれるように、展示会や個展などをに参加し続けています。

OMBLE:最後までお読み頂きまして誠に有難う御座いました。
「般若面」が有名な平松さんですが、見るものを圧倒する鬼裂文・亀裂文シリーズ、太古の生命力を感じる黄鉄鉱アンモナイトは必見です。植木鉢の取扱は弊社のみで、次回の納品は23年の冬を予定しています。点数は少ないですが、是非手にして下さい。
平松龍馬 https://omble.base.shop/categories/4806857