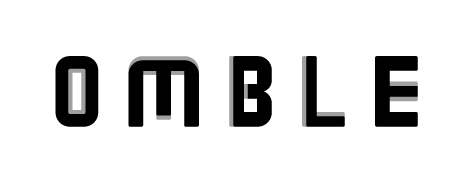2022/11/16 22:53
澄んだ高い空に鱗雲がレースの如く覆う晴れた日に、陶芸家・竹内真吾さんを訪ねて愛知県瀬戸市を訪ねました。
陶芸家になるまでの道のり
私は生まれも育ちも瀬戸です。
当時は製陶所が立ち並んでおり、子供の頃はその周辺が遊び場でした。
今では考えれませんが、焼き損じた作品が川などにそのまま廃棄されていて、それを投げたりして遊んでいました(笑)。量産用の重油窯が沢山あり、地面の中をくぐって煙突が立っていて窯を焚くと地面が熱くなるんですね。そうすると芋を持ってきて、地面に埋めて焼き芋にしていました(笑)
このような少年時代を過ごしたお陰で、土に対して全く抵抗がありませんでした。
サラリーマンを3年間経験した後、当時の愛知県立窯業訓練校に入学し、1年間陶芸を無料で、失業保険の延長給付を受けながら学びました。高度経済成長時代の1979年頃、脱サラという言葉が流行っていました。同じクラスには焼き物をやりたい!と言った熱意を持った学生が多く、卒業するころには陶芸で生計を立てようと決意していました。
卒業後、薪窯やガス釜を扱っている窯元で2箇所、合計3年間弟子入りをして仕事を学びました。そして独立。2年目には各地からお仕事をいただけるようになり、有り難いことに40店舗ほどからオーダーを頂いたり、国内外での個展やグループ展などで発表させて頂いたりして、今年で独立40年目の節目となりました。

竹内先生の作品について、作陶の手順を教えて下さい
独自のブレンドをした赤土を土練機に掛け、細い紐状にした粘土を積んで成形をします。つまり轆轤は使用していません。土の塊で小さなモデルを作り、それを見ながら制作しています。これは「紐作り」と呼ばれる技法で、小さな作品でしたら30分程度、少し大きな植木鉢だと1時間程度で、完成後の形状を想定しながら積んでいきます。
削る際にエッジ部分に穴が空いてしまったりするので、完成後の形状を考えながら(厚い部分がなかなか乾かない、薄いところが早く乾いてしまう、では支障があるので)出来るだけ同じ厚みになるように積んでいきます。
季節によって変わりますが、積んだ翌日から削り始めることが多いですね。

特徴的な「削り」について教えて下さい
だいたい1作品につき2~3日かけて、主に鋸歯とサフォーム、ツゲを使って削ります。
柔らかい外側から硬い内側を削ることになります。出来るだけ厚さが均一になるように、更に削っていくと工具を変えたりするので、土によって、形によって削る方法を変えています。日々、削って乾燥させてを繰り返してシャープなエッジを出しながら完成に近づけていきます。
削り終えたら、完全に乾燥をさせます。
乾燥にストーブなどは使わず、タオルや、作品によっては毛布を掛け、じっくり時間をかけて自然に乾燥させます。乾燥後、800℃くらいで素焼きをします。
素焼きをした後に、鉄分が多い泥状の化粧土を作品全体に塗って、すぐに拭き取ります。拭き取ると、エッジ部分に鉄化粧土が残り、完成後の黒っぽい線のようなデザインとなります。
その後、溶けない釉薬(アルミナと木灰を混ぜたもの)を刷毛で塗って、本焼きまでの準備が完成となります。

本焼きと冷却還元について教えて下さい
ガス窯を使用しています。

本焼きは950℃前後で還元をかけ1250℃まで温度を上げます。
釉薬が溶ける温度や土が焼き締まる温度まで上げきると、そこから自然に冷ますのが一般的ですが、そうすると直ぐに炉内が酸化状態になり、酸化すると茶色く変化してしまいます。
私の場合、窯の中の温度を均一にするために、一時的にある温度帯でこの酸化を利用します。
温度を下げる際、ガスを入れ還元をかけたまま900℃くらいまで焚き冷ましをしています。これを「冷却還元」と呼びます。冷却しながら還元し続けることによってコンクリートのようなグレーや黒っぽく見た目になります。900℃からはガスを切り自然に冷ませます。ガス窯を使っているので、電気窯のようなマイコン機能はついておらず、本焼き中はガス圧や温度は自分で図を書いて管理しなければなりません。

成形した土や入れている作品によって異なりますが、だいたい150℃~100℃で窯を開けて取り出します。
取り出した後の作品は下の写真右のベージュのような色で、ワイヤーブラシを使って溶けない釉薬を水を流しながら剥ぎ取ると、左のコンクリートのようなグレーや黒っぽい焼き締めの作品が出来上がります。

OMBLE :最後までお読み頂きまして誠にありがとうございました。
瀬戸で作陶されている世界的に有名な作家の竹内真吾先生。
上記のレポート通り、成形から乾燥、削り、本焼きまで手間暇を掛け、完成した作品はまさに開放された自由を表現した美術品です。
無骨にしてシャープ。お気に入りの植物を添えるにはこれ以上の無い植木鉢だと確信しました。