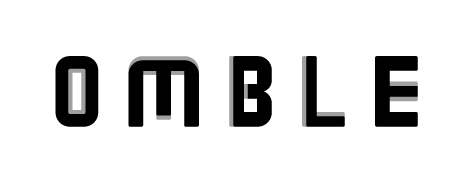2022/11/12 05:42
一年に一度、長江寺の穴窯に火を入れる秋晴れの日に、陶芸家・川合牧人さんを訪ねました。
川合氏の作陶の手順について質問させて頂きました。
是非お読みになった上で、お気に入りを手にして下さい。

どのように成形しているのですか?
基本的に殆どの作品を電動ろくろで成形しています。
成形後、植木鉢本体の削り作業を行い、乾燥させて素焼き準備となります。
脚付きの作品の成形方法を教えて下さい
植木鉢本体を成形してから、本体の勾配の角度を取って型紙に沿わし、粘土の板に当てて粘土を切って脚を3つ作り、本体と合わせます。重厚感ある本体を3つの脚で支えるので少しリスクがあり、稀に焼いた時にヒビが入るときがありますね。
土と土をくっつける時に気をつけるのは、お互いがほぼ同じ乾燥具合の時に合わせる必要があるので、土の乾燥具合を確認する必要があります。
素焼きをする前に、植木鉢本体と脚をくっつける作業を行った後、完全に乾燥させて素焼きをします。

素焼きから本焼きまでを教えて下さい
作品によっては、(素焼き前に)下地としてドロッとした鉄分を含んだ粘土を柄杓で掛けて、焼き上がりに違う景色が出るようにする作品もありますが、通常は成形後、素焼きをします。だいたい750℃です。
素焼き後、私のオリジナル「白礫釉(はくれきゆう)」を柄杓またはズブ掛けして本焼きです。そうすると取り出した際に「真っ白」になり、その縮みが「ひび割れ」したようなクラックが作品に入ります。クラックや貫入は収縮の違いによって生まれます。これが作品の一つの特徴です。
窯は、電気で火を入れて、950℃くらいになったらプロパンガスを突っ込んで、還元雰囲気、酸素不足の状態にして景色を作ります。もし染め付けだったら青が綺麗になるし、茶色だったら濃くなりますね。これが本焼きです。

「漆を塗る」この作業を教えて下さい
天然漆を使い、作品全体を黒く仕上げます。
天然漆はウレタン漆と違い、非常に高価で、その技法は貴重です。
まずお盆に漆を入れ、琥珀色の漆を「松の灰」で黒くします。
硬めの刷毛で作品の全体に塗りますが、縄文中期にはあったと言われる「陶胎漆器」と言われる技法を使って仕上げています。現代陶に4500年前の技法で生まれたテクスチャーを楽しんで頂きたいです。
作品をよく見ていただくと、撥水剤を掛けている脚や高台も含めて全体に漆を塗っています。脚も含めて漆を塗ることで、引っ掛かりもなくなり台に優しく、傷つける可能性が低くなります。また、漆は乾くと強度があるので、一見すると剥がれ落ちそうなクラック部分が剥がることもありません。
私のサインを天然漆に白い顔料を混ぜてベージュっぽい色に調整して、一番最後に書いて完成です。

穴窯について少しだけ教えて下さい
長江寺さんのご厚意で敷地内に穴窯を建てる許可を頂き、17年前に3ヶ月かけて築窯しました。かなり大きい穴窯なので、1年間に1度だけ、中に200~250作品を入れて焚きます。他の陶芸家さんの作品も焼きますし、陶芸教室の生徒さんの作品も一緒に焼きます。
薪は赤松を使い、950~1000℃になれば還元にし、1250℃を目指して65時間から70時間、用意している大量の薪が無くなるまで焚き続けます。一人では出来ないので、沢山の人たちに助けていただきながら焚いています。焚いた後、煙突も含めて蓋をして、取り出すのは1週間~10日後です。それまでは燻製状態です。

OMBLE :最後までお読み頂きまして誠にありがとうございました。
川合様、年に一度という穴窯の火入れにお邪魔したにも関わらず、お時間を作ってお話頂きましてありがとうございました。
穴窯で焼成された作品にも非常に興味があります!またお話を聞かせて下さい。
川合牧人 https://omble.base.shop/categories/4764052