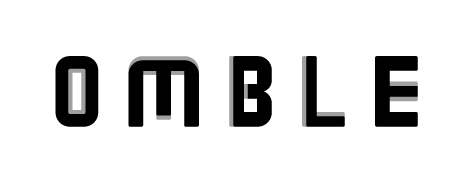2022/11/02 16:53
陶芸作家 須釜優子氏 インタビュー(三重県伊賀)
短い秋が訪れた束の間の晴れ間、須釜優子さんにお会いしました。
伊賀焼で知られる土地に移住し、作陶する。その想いなどをお聞きしました。
最後までお読み頂いてから、改めて作品をご覧頂けたら嬉しく思います。

陶芸との出会いまでを教えて下さい
須釜優子と申します。生まれは埼玉県です。
小学生の頃から割り箸で植木鉢を作ったりするほど、図画工作好きでした。
小学生5年生で人生の転機が訪れたのです!
父親の仕事の関係で、インドネシアのアチェに家族で移住しました。
セスナ機しか飛んでいないような田舎です。家の前にコモドオオトカゲみたいのが這いずっている…そんなところでした。
インドネシアでのインターナショナルスクール(授業は英語!)やインラインスケート、オリエンテーションで山遊びなど、本当に刺激的でしたね。
アチェでも陶芸が盛んで、ものづくりをしていました。
帰国して中学を卒業後、またも急に人生の転機が!
高校入学後、今度はシンガポールに3年間移住することになりました!
気づけばこのシンガポール時代に母親と通っていた陶芸教室のお陰で、ものづくりは「陶芸」という考えになりました。
帰国後、東洋大学哲学科に入学しました。
哲学っぽい文章を読んだり変なことを考えるのが好きですした(笑)
学生時代は、陶芸やガラス作り体験を通じてものづくりをしていましたが、趣味の旅行を楽しみました。
時に民族衣装を着てインドやベトナム、トルコなど、世界を旅しました。
旅行会社勤務や添乗員などの仕事を3年ほど経験しました。色々有りましたが長くなるので割愛させて頂きます…。
常に胸の中にあったものづくりに対する気持ち、陶芸家への道を目指そうと決意し、京都伝統工芸大学校の陶芸専攻の門をたたき、3年間学びました。
アパートの壁に、「陶芸家になる!」と書いた紙を貼っていたほど気合が入っていました(笑)
伊賀焼陶器まつりで陶芸家・谷本洋氏の作品と出逢い感動、運良く出ていた求人に応募し、晴れて師匠の弟子になりました。
陶芸家の「弟子」について教えて下さい
谷本洋師匠に弟子入りし、三重県伊賀市に移住しました。
朝は犬の散歩からお掃除、草むしりを1時間くらいします。1時間です!雑草の生命力は凄いです、侮れません。
決して除草剤は使わず、ひたすら手で毟ります。特に石の間の草は丁寧に毟っていました。
途中から住み込みになり、朝食を任されるようになりました。朝食後、工房やギャラリーでの勤務となります。
師匠は作陶に集中しているので、滞りなく制作できるように、仕事・生活両面をサポートする感じですね。
工房で師匠の作陶作業をチラ見し盗み見しながら学んでいました。仕事後に作った作品を師匠にお見せして頂いたご意見を元に作陶する日々でした。
だいたいの弟子は3年いれば卒業するんですが、私は色々タイミングが重なり13年もいました(笑)
師匠と一緒に轆轤をするような事は無かったですが、最後の方は作陶作業をビデオで撮影して勉強させて頂きました。
そして、徐々に自分でお金が稼げるように仕事をシフトしないといけないね、と教わり独立に向けて歩みだしました。
伊賀はどのような土地ですか
そうですね。まず、山が近い。そして雲が近いです。
なといっても景色が良いことに毎日感動します。「四季が濃い」ことにも感動しますね。
春から秋にかけて虫が多いのがちょっと…ではありますが。

伊賀は四季が濃いとの事。では、好きな季節はいつですか
好きな季節は夏ですかね。
東南アジアに長くいたことも理由でしょうか、工房はエアコンがついていますし、水も心地よい温度で快適です。
冬も好きですね。ただ土がとても冷たくて手が真っ赤になります!お湯で冷たい手を温めて…の繰り返しですね。
自宅からアトリエに向かう僅かな間に感じる季節感が好きですね。
有り難い事に、春と夏はイベントや外出が多く、どちらかと言うと「外に向かう時間」。特にイベントでお客様と直接お話すること自体が楽しいですし、次の作品のヒントやアイデアが生まれます。
夏と冬は、貯めたアイデアや作りたかったものを実現する季節です。
どちらかと言うと長期間作業に没頭できるので、作りたい作品を作り、ゆっくり自分と見つめ合う時間なので好きです。
あと、春は花粉症です(笑)
どのような作品を作られていますか
主に、うつわ、茶器、花器、酒器、そして植木鉢を作っています。
今後は伝統的なお茶道具を作っていきたいと思っています。
来年は独立後初めての個展を京都で開催する予定です。
BaseでUgamaというネットショップを運営しており、そちらで購入することができます。
植木鉢は、OMBLE さんを通じて是非購入して下さい。

作陶の手順と伊賀焼の特徴を教えて下さい
はい、私は伊賀焼を学び、作っています。
伊賀焼とは、伊賀の土を使い、焼べる薪(赤松)の灰がかかった箇所が溶けたり窯変したりして、「景色」ができる焼き物です。
二つと無い「景色」が魅力です。
作陶の手順は、ほとんどの場合が白土なのですが、伊賀の土を使い、手びねりや電動ろくろで成形して、乾燥後に削ります。
素焼き後、水で溶いた赤松の灰を仕上がりを想定しながら作品にかけた後、灯油窯で焼きます。
無煙窯で焚く場合は、素焼き後に何も掛けずに薪窯で焚きます。釉薬は使いません。
是非、見て頂きたいところは、伊賀焼ならではの景色。ビードロの色合い。ゆがみや文様、灰かぶりや焦げなどの総合的な美。
また、よく伊賀焼は「破調の美」と呼ばれます。綺麗に成形した後に、崩しながら歪ませてバランスを取るのが伊賀焼です。
(補足:琵琶湖に堆積してできた亜炭等を含む伊賀陶土と燃料の赤松を使って、ヘラ目や押し型、耳などの個性的な意匠や、整った形に手を加えて歪ませた破調の美が見られる作品。灰が溶けて緑のガラス質となったビードロや灰かぶり、焦げや山割れなどが自然の窯変の結果のように見えるが作家は想定して焼いてる。1982年に国の伝統工芸品に指定。)
須釜さんが築窯した「無煙窯」について教えて下さい
無煙窯とは、黒鉛を二次燃焼させて不純物を燃やすことで、煙が出ない、「無煙」になる薪窯の事です。
伊賀焼に魅了されて弟子入りし、「いつかは窯をもつ!」と誓い、独立後ようやく自分の理想の窯を造りました。
今年、2022年の7月末に完成して、8月に初めて焚きました。
初めての窯焚きは感動でした!大感動!無煙になった時は本当に大感動でした!本当に煙がでないー、ってなりました!
自分の窯ながら焚き方も、窯詰めも、今までの窯と違うので師匠にアドバイスを頂きながら。
無煙になったとき、最後の作業が終わった時、感動しすぎて号泣しました…。
無煙窯は炉内上部に沿道を設置して、900℃~1100℃に達すると沿道内で黒鉛が二次燃焼し煙が完全に消えます。
その温度に達するまでも煙は少ないです。
伊賀焼は通常3日間ほど焚きますが、無煙窯の二次燃焼を利用する構造上、熱効率もよく2日間ほど焚きます。
時間が短縮できるので、大切な薪の量も節約できます。その後、2日間くらい冷まして作品を取り出します。
私が炉内に入りますが、窯の各所に薪をくべる穴を用意しているので怖くなく、窯出し作業も安心です。
宮大工さんに設計・建築してもらい、宮大工さんの試作、長野の陶芸家さんに次ぐ、日本で3つ目との事です。

なぜ無煙窯にこだわりがあるのですか
作陶には、伊賀の土を使って、水を使い、薪を使って完成します。
有限なものですから、作業を通じて、出来るだけ環境にやさしくありたい、そう思っています。
例えば、石鹸を使うようにしたり、除草剤を撒かないようにしたり。
無煙窯も、脱炭素化に少しでも貢献出来れば。薪も効率よく使えれば。
今後は、無煙窯の窯焚きで出きた灰を二次利用して作品に使っていく予定なんです。
来年は5回焚くのが目標です。
試すことが沢山あるので、定期的に焚いて「自分の窯」にしなければいけないと思っています。

植木鉢に関しての思い
先程の通り、伊賀焼ならではの「景色」をお楽しみ頂きたいです。
左右対称で綺麗に削られた美しい陶器鉢が沢山ありますが、私の作品は、正面と後ろ、もっと言うとどこから見ても「景色」が違うので、ぐるぐる回して楽しんで下さい。
自然の窯変に植物を植える美しさ。ビードロが強い面、灰っぽい面、あまり灰がかかっていない面など、気分によって変えて植物を育てて頂ければと思います。
伊賀焼は個性的なヘラ目や押し型、耳、繊細な模様などがありますので、そのあたりも楽しんで頂ければと思っています。

OMBLE :最後までお読み頂きまして誠にありがとうございました。
太陽光が差し込むモルタル床と木材が温かな雰囲気の美しいアトリエで、四季が濃いと言う伊賀で作陶されている個人作家の須釜優子さん。
無煙窯へのこだわりや環境への配慮という点において共感し、私も非常に勉強になり取り入れたい、取り入れないといけないと感じさせられました。
力強くもどこか優しく暖かい作品は、きっと人柄から溢れてきているのだと思いました。