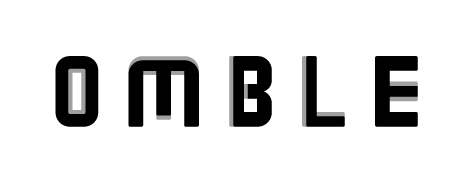2022/11/02 05:46
九州の人々が初めて冬を感じたであろう日、山下太さんにお会いしました。
世界最大級の活火山で知られる熊本の阿蘇で生活し、作陶する、その想いなどをお聞きしました。
最後までお読み頂いてから、改めて作品をご覧頂けたら嬉しく思います。
憧れの陶芸作家さんを訪ねて、熊本の阿蘇へ
この度、OMBLEにて陶芸家 山下太氏の作品を取扱う事になりました。
一輪挿しの販売から、植木鉢の販売までを予定しています。個人的に大好きな作家の一人で、店主憧れの陶芸作家でもあります。
熊本県の阿蘇山に麓に素敵なアトリエを構え、強いこだわりをもって作陶されています。
今回、山下さんを訪ねてお話をお伺いしてきました(山下さんのお出迎えよりも先に、なんと猪が迎えてくれました!)。
火山の麓、阿蘇で、どのような想いで、どのような手順で作陶しているのか。
お読み頂いた上で、手にとって頂ければと思っております。

山下氏と阿蘇について
福岡県の小石原の窯元で修業し、阿蘇五岳の麓に移住。
20年以上に渡り、溶岩や火山灰、土、水、草木など、阿蘇山の自然の素材を活かして作陶されています。
繊細な技術がありながら、地球のスケールを感じさせる力強い作風が魅力で、個人的に大好きな陶芸作家です。
阿蘇山は周囲128㎞もあり世界最大級の火山活火山。
阿蘇五岳を中心にした東西にのびる連山を指しますが、広い意味では火口原を含めた呼び名です。
この火口原には約5万人が生活していて、田畑が開け、国道・鉄道が通っており、山下氏のアトリエがあります。
この火山が未だに噴火しており、火山灰、溶岩などを噴出。
頃合いを見計らって山下さんが、「箒とちりとり」を持って火山灰や溶岩を採集されます。
噴火によってそれがドロドロだったりサラサラだったりするそうです。
私たちの記憶に新しいのが2021年の噴火で、火砕流が流れ下り、一部には被害が出てしまいました。
その時に舞い降りた火山灰や溶岩を使い、作陶し、作品として生まれ変わるという壮大なストーリーがそこにはあります。

作陶の手順について
阿蘇山から赤土を掘って、作陶しています。
全て同じ色味ではなく、掘る箇所によって若干色が異なります。
どの土を使うかは、完成後の色味を想定して判断したり、作品に応じて阿蘇の土を使い分け、作品によって、天草の土も使っています。
作陶手順は、まず轆轤で成形して乾燥させ、削って素焼きし、独自の釉薬をかけ電気窯で焼くという手順です。

こだわりについて
山下氏のこだわりは阿蘇の土を使っている事だけでは有りません。
一般的な陶芸家が利用している、市販されている釉薬や撥水剤は「一切」使いません。
作品が構成される、全ては「自然からの恵み」なのです。
日々、広大な阿蘇山を周回し、箒とちりとりを持って火山灰や溶岩、草木などを独自の釉薬にして利用しています。
阿蘇に移り住んで20年以上、たいがいの自然のものは釉薬として実験したとの事です。
火山灰とか溶岩や笹の葉などの草木を自然の中から探して、独自の釉薬を作る。
最近では昨年(2021年)大噴火した際の溶岩や火山灰でだったり。草を灰にしたり、笹を灰にして釉薬にしたり。
それらの釉薬を組み合わせて、更に一度ではなく何回かに重ねて焼成する事で、独自の作品となります。

作品に懸ける想い
まず殆どの作品は成形し、削りをして素焼きをして固めます。
作品によってはそこから、
白い化粧土を上から掛けて、それを水につける事で、付けた白い土を自然に剥がし縮れヒビを入れ、1200℃で焼成。
この水をつけて化粧土が自然に剥がれるのすが、剥がれ具合が非常に重要で、バランスが悪いと何回も水につけては剥がす、を繰り返すします。
焼成し冷ました後で、独自の自然釉薬をチャッポンと掛け、再度焼成し冷ます。
異なる自然釉薬を掛けて再度焼成。
この手間暇を「繰り返す」事で、何層にも重なったような色合いを、納得がいくまで出す、こだわりと想い。
一つの作品に5回程度焼くこともあるそうです。

OMBLE:
最後までお読み頂きまして誠にありがとうございました。
雄大な活火山と共に生活し、活火山が残した自然を使い作品として新しい魂を吹き込んでいる山下氏。
阿蘇にこだわり、自然にこだわり、市販されているものは一切使わないという強いこだわりとそのストーリー。
丁寧で繊細でありながら地球のスケールを感じる雄大な作品を、一生ものとして迎えて下さい。
山下太 https://omble.base.shop/categories/4762928